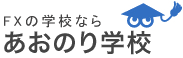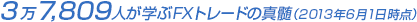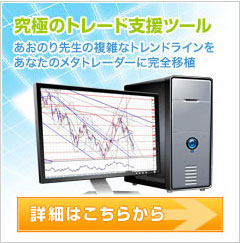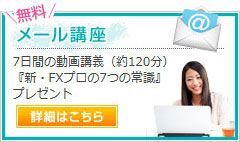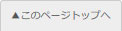ドル円買いの成功可能性低下?
ドル円は一時90円を超えていたが、
今では88円まで低下している。
このような中でドル円でロングを採用する場合、
次のポイントが警戒されたわけだが、
買いを警戒できたポイントとはなにか?
↓
http://aonorifx.com/a20130123.html
こんばんは、あおのり先生です。
いつもメルマガをご活用いただき、誠にありがとうございます。
ドル円は買い過熱感が出ているということは
あおのり学校ブログでも指摘していた通りなのですが、
その根拠としていた分析手段は「RSI」を参考にしていたからです。
※あおのり学校ブログでいつも表示しているチャートの下に表示してあるテクニカル指標がRSIです。
ちなみに、RSIの計算式は以下のとおりです。
RSI = 値上がり幅の平均÷ (値上がり幅の平均+値下がり幅の平均)×100
要は相場の価格に過熱感がでているか否かを教えてくれる単純なツールです。
RSIで70%を超えれば割高感があることを表すのですが、
ドル円日足チャートベースでみると一時90%前後にまで上昇しており、
買い過熱感が出ていました。
この指標から買い過熱感は明らかであり、
ドル円が崩れやすい兆候がでていたためです。
ですが、
日足RSIの70%超えは去年の10月からも表れていることです。
日足のRSIだけを見て『過熱感が出ているから』とショートを仕掛ければ、
ドル円で10円以上のマイナスにもなってしまうほど、
方向感が出た時は役に立たない分析ツールでもあります。
このように、
RSIを教科書的な使い方しかしらなければ大火傷を負いかねないのは事実です。
本屋で売っているレベルのFXの教科書的な書籍レベルの使い方では、
テクニカル指標の本当の使い方がわかるはずもありませんし
実践的な使い方は載ってはいないものです。
単純にFXのやすっぽい教材を信じてRSIを過信すれば大損の素ですが、
見方がわかればこれほど価格の動きを精度高く教えてくれる
役立つ分析ツールもないのですが、、、
では、
なぜ日本にはそのような実践的な投資本が少ないのか?
投資をしなくてもお金を増やす手段が日本には今まではあったし、
日本人の国民性から見ても投資には否定的だったことが原因でしょう。
銀行にお金を預けておけば1990年から始まったバブル崩壊を少し過ぎるまでは
約5%かそれ以上の銀行金利がついていたために、
リスクを取って投資にお金を回す必要がなかったからです。
100万円を銀行に預けていれば、金利だけで年間5万円がもらえた時代でしたから、
今のゼロ金利からは想像もできませんね。
それに、
私と同年代くらいの若い方にはピンとこないかもしれませんが、
40代以上の年代の方にとっては汗水流して働くことが労働の美徳と考えられ、
投資に対する偏見が今までありました。
農耕民族という国民性からも、リスクを恐るのは仕方がないでしょう。
しかし、
今の時代は銀行は低金利時代であり、
汗して長時間労働してもお金が増えない時代に完全に入っています。
額に汗して働く単純作業ほど、アジア後進国やネットで代替されています。
むしろ、多少のリスクを犯してでも想像力を働かせて行かなければ
お金を増やしていけない時代です。
投資もイマジネーションです。
今回はチャート分析の話をしましたが、
相場観から見てもプレミアム会員様や1月のセミナー参加者様にお伝えたとおり、
ドル円は下落しているでしょう?
想像力があれば価格の動くシナリオを立てられ、
未来予想精度は高まるはずです。
たとえば、
2013年度は去年の12月中に開催した“投資に役立つ占いのセミナー”で伝えたとおり、
2013年に起こる現象として天災や戦争が増えることをしていました。
実際に中東・アフリカではマリやアルジェリアにまで内戦が拡大したり、
東アジアでも中国は『日本との戦争に備えよ』とまで国民向けメディアで煽っているように、
東アジアでも尖閣をめぐる局地戦も、
占いや世界情勢の変化から見ても高い確率で起こりえます。
戦争が起きることを見越せば、軍需産業の三菱重工業が買いかな
では先回り買いしておこうとかいうのがイマジネーションのある発想です。
※投資と同様に、占いの中には未来を予想するものもあります。どちらも未来を予想している関係上、
当たるも八卦、外れるも八卦と言われるのは仕方がありません。絶対当たるなどないですから。
しかし、この占いは世界の兆万長者も参考にしているくらいです。
このような相場観は経験が必要なので一朝には身につきませんが、
チャート分析に関しては実践的なRSIの見方レベルならすぐに身に付きます。
投資のチャンスが2013年からは訪れている兆しがでていますので、
早い段階で投資力を磨かれてチャンスをつかむコツを
あおのり学校プレミアムで身につけておくと良いでしょう。